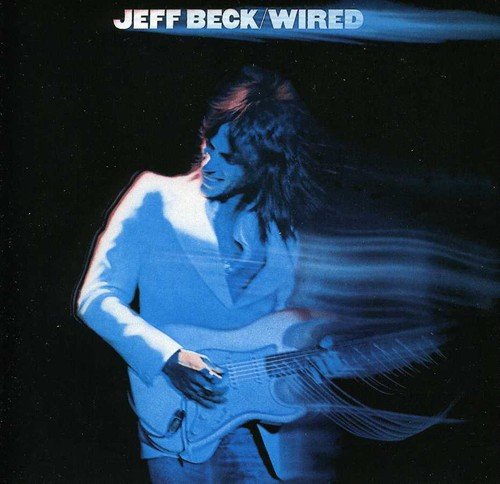01 Led Boots
02 Come Dancing
03 Goodbye Pork Pie Hat
04 Head For Backstage Pass
05 Blue Wind
06 Sophie
07 Play With Me
08 Love Is Green
1976年5月リリース
Produced By George Martin
Except Blue Wind Produced By Jan Hammer
<メンバー>
Jeff Beck:guitars
Max Middleton:Hohner clavinet (except on “Blue Wind” and “Love Is Green”), Fender Rhodes electric piano (on “Sophie”)
Jan Hammer:synthesizer (on “Led Boots”, “Come Dancing”, “Blue Wind” and “Play with Me”), drums (on “Blue Wind”)
Wilbur Bascomb:bass (except on “Blue Wind”)
Narada Michael Walden:drums (on “Led Boots”, “Come Dancing”, “Sophie” and “Play with Me”), piano (on “Love Is Green”)
Richard Bailey:drums (on “Goodbye Pork Pie Hat” and “Head for Backstage Pass”)
Ed Greene:second drum kit (on “Come Dancing”)
こんなにテンションの高い演奏をするギタリストがいただろうか嫌いな人には全編雑音の洪水、好きな人には感性のビタミン。重箱の隅をつつくような聴き所もいっぱいあります。
インスト路線に転じた2作目ですが、前作よりもっと追求度が高まったという感じです。何かに向かって突き進んでいる。ここでは、前作のモチーフと言われているマハビシュヌオーケストラ関係者が参加しています。ヤンハマー、ナラダマイケルウォルデン、彼らの凄腕がジェフベックを刺激し、テンションは高まりまくっています。全体の出来自体は、前作に比べて荒削りです。しかし、それがまたライブ感を醸し出しているところもあります。
前作がファンクをベースに、よりエモーショナルにギターサウンドを展開するといった組立になっているのに比べ、本作では、表現したいギターサウンドのイメージを中心におき、それに状況作りをしていったというようなところが感じられます。リフのつくりかたやギターソロへのアプローチなど、ギターサウンドのための曲といえそうなものが多くあります。しかし、実際はそれほど統合的にはつくられていないんでしょうね。優れたミュージシャンが思いつくままにセッションをして、ベックのギターがうまく響くやつを集めた、そんな感じなんでしょうか(ほとんどのアルバムは、そんな感じでつくられるんでしょうが)。
いずれにしてもジェフベックのキャリアの中で、ある意味で頂点を極めた感のあるアルバムで、ここからベックファンになった人や、ジェフベックと言えばワイヤードのイメージを持つ人も多いんじゃないでしょうか。ベックも当時は32歳一番脂がのった時期だったのかも知れません。次にでるライブでもそのエネルギーは感じられます。
ワイアードは、ジェフベックのアルバムとして出ていますが、言ってみればマハビシュヌ軍団とのセッション集みたいなもんです。
*追記:マニアックに聴きたい方に
このアルバムはQuadraphonic盤があり、ミックス違いが聴けます。Come Dancing、Head For Backstage Passなどは通常版では聞こえないギターが聴けます。
Led Bootsは、ドラムの音が分離していて通常版よりクリアに聞こえ、ベックのサイドギターの音も大きくミックスされています。
Play With Meのサイドギターも良く聞こえます。
各曲紹介
<SIDE A>
1. Led Boots
いきなりこのアルバムのハイライト。もうどうしてこんなにカッコイイリフがつくれるのか(作者は確かマックスミドルトン)、どうしてこんなにすごいドラムが叩けるのか、ベックのギターも爆発寸前という感じ。これ、録音するとき、相当でかい音でギターを鳴らしていると思われます。後半、キーボードソロのバックでよく聴くとギターのチャンネルからピーピーとハウリングしている音が聴こえます。
一般的には、これはノイズのあるテイクとして没にしてしまいそうですが、ジェフベックならそのままOK。こういうところがジェフベックの味でもあります。
また、この曲のもうひとつの聴きどころは、なんと言ってもドラムです。オープンとクローズドのハイハットワークなどを駆使して、まさに息をもつかせない、たたみみ込みようなドラム。これ以後のどのライブテイクよりこのスタジオ録音の方がすごいという珍しいケースです。今やマライヤキャリーなどのヒットプロデューサーとなってしまったナラダさん。また、ドラムを叩いてほしい(→2010年からのジェフベックのバンドで叩いていました)。
その他にももちろんヤンハマーのミニムーグシンセ。このミニムーグというのが、シンセのくせして独特の音色を持っているんですね。また、ヤンハマーは独特のフレージングをします。今では珍しくもなんともないピッチベンダーを使ったギター的フレーズですが、当時は、とても新鮮でバカテクでした。また、バッキングのクラビネットが独特のつまり具合を出していて、ポイントのひとつです。とにかくのっけからこんなにテンションがあがってもいいのでしょうかというトラックです。
この曲は良く聞くとドラムが1拍ズレているように聞こえます。あるミュージシャンの話では、ナラダマイケルウォルデンがリフの捉え方を1拍ズレて捉えていたからだと言う話です。これは、実際にレコーディングをしたベーシストが話していたそうです。そういう耳で聞くと冒頭のドラムのフィルも納得いくような気がします。
また、この演奏は実はイントロがもっと長かったそうですが、LPに収めるために切ったという話です。だからいきなり変なドラムの入り方をしているという事なのでしょう。
2. Come Dancing
この曲は、ひとつ革新的なところがあります。ジェフベックがブラスを入れたのはこの曲が初めてです。ドラムがツインドラムで非常にいいノリ。この曲でのギターの聴きどころは、オクターバーによるソロです。それも1オクターブと2オクターブを切り替えながら弾いています。一般的なオクターバーでは切り替えることは出来ないんですが、ベックの使っていたカラーサウンド(メーカー名)のヤツは、改造してありました。
ここでのフレージングも、ジェフベックらしいもので、ジャズの人なら、ややこしいスケール を使って流暢に弾きこなすところですが、ジェフベックの場は、”ギター界の中学校レベルの英語”とでもいっていいようなペンタトニックで、コードごとにキイを変えてギクシャクと弾いていますが、このぎくしゃく感が独特の無骨さとエモーションを醸し出していていいんです。車で言えば、アルゴノミクスデザインの現代車より、昔のアルファロメオがかっこいいみたいな感じでしょうか。
3. Goodbye Pork Pie Hat
第二期のデフィニトリーメイビーと同じようなリズムの「聴かせ曲」。ベックのギターを聴かせるのにちょうどいい「間」ができるリズムです。言わずと知れたジャズの巨匠チャールスミンガスの曲で、こういう曲をベックがとりあげるのも、マハビシュヌ軍団の影響かも知れません。トーンコントロールやボリュームを頻繁に操作して様々な表情をつけます。この辺がベックの醍醐味。ライブでもこの曲は聴きごたえがあります。ただこの手の曲、アマチュアバンドがやるとギターはうまくても、もう一つだったりします。バッキングがとても重要なんですね。特にベックバンドでは、ベックのギターがうまくぽこっとはまるような音の空間をあけてあげるのが大事です。さすがこのメンバーはうまいです。
4. Head For Backstage Pass
このくらいの16ビートは、ベックのたたみかけるようなフレージングの演奏環境としては抜群です。連続トリルもきれいに決まるし、まるでベックギター講座のエクササイズに用意されたみたいな曲です。ソロではいかにもベックのフレーズの連続です。しかし、ライブではこの曲聴いたことがありません。あまりダイナミックなノリがないので、小さなホールならいいかも知れませんが、ベックはたいがい大きなところなので、合わなかったのかも。それに、決めのフレーズをどうしても一緒に弾くことができなかったのかも知れませんね。 それが、一番の理由だったりして。
<SIDE B>
1. Blue Wind
ヤンハマーとベックの2人だけで録音したということで当時話題になった曲です。作者は、ヤンハマー。この人は本当にこの手のリフをつくるのがうまい。キーボード界のジミーペイジのような人です。しかし、ドラムは勘弁してほしい。これドラムがちゃんとしていればもっと良かったのにと惜しまれるところです。
2. Sophie
この曲は、何ともいえないメランコリックな味わいを持っています。素敵なメロディとハーモニーの展開で、そちらの方に比重が行ってしまって、フリケンシーモジュレーターを使ってハードに展開するベックのソロはあまり前にでてきません。どちらかと言うとベンチャーズ的にメロディ弾きを聴かせたかったのかな。でも、これ、ベックと言うよりマハビシュヌって感じですねどね。
で、ブートレグのセッション集を聴くとこの曲には、もっと長く美しい前奏があるのです。収録版は、前奏の途中からになっています。残念です。A面に比べ次の曲とこの曲の2曲は、このアルバムの中でちょっと特異な存在の曲です。
3. Play With Me
ファンキーなクラビネットから始まります。マックスミドルトンは快調ですね。この曲もテーマメロは哀愁を帯びたメロディ。夏の終わりをイメージさせます(私だけかも)。でもベックは全くソロを弾いていないんですね。これも前の曲と同じようにベンチャーズ的なのかも知れません。メロディとサイドギター。でもこれが結構味わい深いんです。聴こえにくいですが、よく左(右だったかな)のスピーカーに耳を澄ませば、ベックが律儀にリフを弾いています。しかし、律儀とはいえ、そこはジェフベック。1回1回ちょっとずつ違います。
4. Love Is Green
恋は水色をパロッたようなタイトルですが、非常に美しい曲です。で、恋は水色以来の生ギターも入っています。中間のギターソロのちょっと歪んだ加減の音色が何ともいえない心地よいテイストです。その音色のまま2回目のテーマメロディ。エンディングも非常にエレガント!これもメロディが哀愁です。B面の後半は哀愁シリーズですね。この曲、あまり話題になりませんが、私の中では、ランキングの上位グループです。